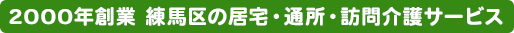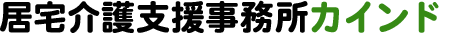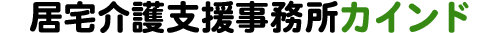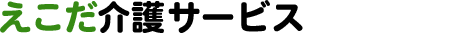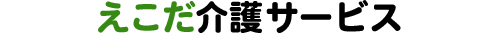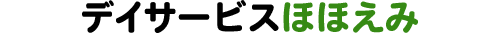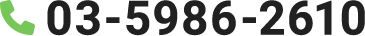居宅介護支援事務所カインド
所長あいさつ動画
みなさま、私どものホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
所長で主任ケアマネジャーの今村純一と申します。
私どもは設立から21年、保険者である練馬区、近隣の地域包括支援センター、介護サービス事業所と良好な関係を保ち、ご自宅で生活されている方々のケアマネジメントを行っております。
私どもケアマネジャーは、みなさまからお話しを伺い、お困りごとをどのように解決するか、解決した後にどのような楽しみのある幸せな生活が送れるかを、みなさまと一緒に考える、そのようなケアマネジャーの事業所です。
私どものホームページをご覧いただき、ありがとうございました。
事業所の概要
基本情報
| 住所 | 〒176-0005 東京都練馬区旭丘2-34-12 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-5986-2610 |
| FAX番号 | 03-5986-2620 |
| メールアドレス | kindkyotaku.yahoo.co.jp |
| 事業所番号 | 1372002731 |
| 特定事業所加算 | 特定事業所加算Ⅱ取得 |
| 営業時間 | 月曜日~金曜日 9:00~18:00 (土日祝、12月29日~1月3日は休業) |
| 職員体制 | 管理者・主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)1名(男性) 介護支援専門員(ケアマネジャー)7名(男性2名 女性5名) 事務員 1名 |
| 基礎資格 | 介護福祉士、社会福祉士、柔道整復師 |
| 開設年月日 | 平成15年(2003)5月1日 |
| 運営理念 | 利用者様本位の介護の推進 介護ニーズの変化に的確に対応した介護水準の維持・向上 当社社員の総合力の発揮 地域連携の推進 安定した経営基盤の確立 |
| アクセス | 西武池袋線江古田駅下車 徒歩約8分 東京メトロ有楽町線・副都心線小竹向原下車 徒歩約8分 ※地図が掲載される |
特長
① 担当制ですが事業所内で情報共有を密に図り、事業所がチームとして関わっています
② 働きやすい環境を整えており、従業者の勤続年数が長いです
③ 開設後21年の実績があり、保険者である練馬区、近隣の地域包括支援センター、介護サービス事業所と良好な関係を保ち、地域になくてはならない事業所となっております
サービス利用までの流れ
まずは、区役所で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請を行います。申請はカインドにて代行することも可能ですので、その際はお申し付けくださいませ。申請後は区役所の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、区役所からの依頼により、主治医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
カインドは、ご利用者様のサービス計画書(ケアプラン)作成を、お手伝いをさせていただく事業所になります。
① 要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
② 認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
③ 審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
④ 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
⑤ 介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
⑥ 介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割
ご利用者様、ご家族様から「「介護支援専門員(ケアマネジャー)はどんなことでもやってくれる、利用者や家族が言うことはなんでもやってくれる」と伺うことがありますが、私ども事業所は介護サービス事業所(ケアマネジャー)の役割を以下と捉えております。
ご本人様、ご家族様からお話しを伺い、生活において支障となっている課題や、その課題の解決方法、そして課題解決後の楽しみのある幸せな生活を、一緒に考えます。
一緒に考えたことをご本人様、ご家族様、介護サービス事業所とケアチームを組み、それぞれが役割を果たせるよう方向性を定めます。
ケアマネジメントの流れ(介護支援専門員(ケアマネジャー)はケアマネジメントを行います)
① 電話で問合せ
お電話でお問い合わせください。
ご自宅へ伺い、詳細をお伺いいたします。
② 自宅で契約(介護保険の利用にあたり契約が必要となります)
居宅介護支援の利用にあたり私ども事業所と契約を交わしていただきます。
重要事項説明書をホームページに掲載しております。
ご本人様、ご家族様から個人情報もいただくことになりますので、個人情報使用同意書をお願いしております。
③ 自宅でアセスメント(情報収集をして困りごとの解決に向けて一緒に考えます)
契約時にご本人様のお困りごと、こうなるとよいと思うこと、こんな生活をしたい希望などを伺います。
併せてご家族様からみたお困りごと、こうなるとよいと思うこと、こんな生活をしてほしい希望などを伺います。
それを踏まえてご本人様とご家族様と一緒に考えます。
④ ケアマネジャーがサービス事業所を提案(解決に向けたご提案)
アセスメントを踏まえ、介護サービス事業所をご提案いたします。
ご本人様、ご家族様でお知り合いの介護サービス事業所がございましたら、その介護サービス事業所を調整いたします。
⑤ 自宅でサービス担当者会議(解決の方向性を共有します)
ご本人様、ご家族様、介護支援専門員、介護サービス事業所、必要に応じて主治医がご自宅で、介護支援専門員が作成したケアプラン原案をもとに解決の方向性を共有し、役割分担を確認します。
ご本人様が主役ですのでご本人様が行う役割もあります、また同居、別居を問わずご家族様にご協力いただく役割もあります。
⑥ 自宅でケアプラン交付
サービス担当者会議で検討したケアプラン原案が合意された後、ご本人様、介護サービス事業所、必要に応じて主治医へケアプランを交付します。これにより介護保険によるサービス利用が可能となります。
⑦ サービス利用開始
サービス担当者会議で確認した役割分担によりサービス利用が始まります。
⑧ 自宅でモニタリング
介護支援専門員は最低毎月1回ご自宅へ伺い、ケアプランに記載のある目標達成に向けての進捗や新たなお困りごとがないかを、ご本人様、ご家族様とお話しいたします。